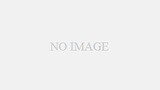<朝夕ラッシュで混み合う「インドネシア通勤鉄道会社」。保有する1000台の車両のほとんどが日本製だ。政府が国産化を目指すなかでも、定着した背景について>
アジア各地で、日本の中古車両が第2の人生を送っている。キハと呼ばれるディーゼルカー、ブルートレイン、客車――。なぜ、古い車両が活躍する物語は「テツ」の心をつかむのだろうか。𠮷岡桂子著『鉄道と愛国 中国・アジア3万キロを列車で旅して考えた』(岩波書店)より一部抜粋する。
◇ ◇ ◇
アジアで日本の中古車両が広く使われてきた背景には、線路の幅の問題がある。
日本の在来線の幅は1067ミリ。第2次世界大戦中、占領した日本がレール幅を統一したインドネシアは同じで、タイ、マレーシア、ミャンマーやベトナムは1000ミリと近い。欧米やロシア、中国、インドなどは1435ミリ以上が中心で、改造するにしても手間がかかる。
インドネシアでは、日本の中古車両が約1000両活躍している。始まりは2000年。都営地下鉄三田線を走っていた72両が、インドネシア国鉄に無償で譲渡された。
インドネシア経済はアジアを襲った通貨危機の後遺症に苦しんでいた。新車を買うお金を節約したかったのだ。
日本側にも、使わなくなった車両を解体する費用を節約できるメリットがあった。鉄道の専門家によれば、日本で30年ほど走った車両でもメンテナンスしだいで、さらに15年ぐらいは走れるそうだ。
活用しているのは、「インドネシア通勤鉄道会社(KCI)」。首都圏を走るインドネシア国鉄の子会社だ。
保有する約1000両のうち、新車は地元の国有企業INKA製の十数両だけ。残りはすべて日本の中古で、JR東日本の205系を中心に東京メトロや東急電鉄で使われていた車両もある。
車体は、赤と黄色に塗り替えられているが、車内に入ると「日本」を感じる。つり革、座席、扇風機、棚、消火器に残る漢字......。
私が乗った車両には「神戸 川崎重工 昭和52年」と書いてあった。西暦でいえば1977年。40年余り前に造られたものだ。乗り心地は悪くなかった。