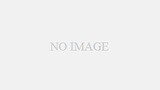信頼できる生産者にフォーカスを当て、その土地でしか生まれない唯一無二のフレーバーとストーリーの生豆を買い付け、日本のロースターへと届けるSYU・HA・RI。
Standart Japan第30号のパートナーを務めてくれた同社のチームメンバーで、地元の群馬でwarmthを営む福島 宏基さんに、SYU・HA・RIのグリーンバイヤーの仕事とコーヒーショップの経営の両立についてお話を聞きました。
これまでの経歴、warmthについて、そしてSYU・HA・RIではどのような役割を担われているかなど、ご自身について教えてください。
この業界に足を踏み入れたのは、2013年だったと記憶しています。エスプレッソ系のドリンクに力を入れていた東京の自家焙煎カフェでの勤務をキャリアの皮切りに、都内で新店舗の立ち上げを複数回経験したり、オーストラリアで数ヵ月間バリスタをしたりしました。東京で6、7年バリスタとロースターを経験した後、兵庫県のコーヒー関連の輸入販売商社に入社し、そこで生豆の輸入や買い付けを担当しました。実はこの時に一緒に生豆の仕事をしたのが、現SYU・HA・RI代表の辻本だったんです。
兵庫県の会社を退職した後、地元の群馬県に戻ってwarmthを開業しました。地元の方はもちろん、老幼男女問わず訪れてくださる全ての方々が「心地よさ」を感じてほしいという思いから、 warmth (英語で「ぬくもり」の意)を運営をしています。
SYU・HA・RIでは、中南米の生産国を中心に買い付けています。業務の範囲としては、実際に現地へ買い付けに赴いたり、オファーサンプルから出荷前検査、到着、プロダクトになるまでの一連の品質管理をしたり、入港後に国内のお客様へ商品の提案や生豆をお届けしたりとさまざまです。warmthとしてSYU・HA・RIの生豆の取り扱いもあるので、カスタマー目線でのフィードバックもSYU・HA・RIにおける自分の役割の1つかなと思います。
コーヒーブランドのオーナーという顔の他に、SYU・HA・RIでのグリーンバイヤーというユニークな働き方をされているかと思います。お店の運営とグリーンバイヤーとしての業務、1日の時間配分や週の活動の中でどのようにバランスを取っているのか、教えていただけますか?
これは一番聞かれることが多い質問ですね。
基本的に普段はwarmthの運営の比重が大きいと思います。もちろん、SYU・HA・RIの国内での対応も日々行っていますが、現地への買い付けやロット選定、入港前後のクオリティチェックなど、1日や週というよりはその時期に集中して業務を行うことが現段階では多いです。
また、warmthとしてイベント出店した際にSYU・HA・RIのお客様とご一緒することも多いので、その際にご使用いただいているロットのテイスティングや、コーヒーのヒヤリング/フィードバックをいただくこともありますね。

お店を経営するということは大変な労力のかかることですが、その上でSYU・HA・RIでのお仕事をしようと考えた目的や背景について教えていただけますか?
前提として、代表の辻本がフレキシブルな働き方を提案してくれたのが大きいです。先述のとおり、日々の仕事においてはwarmthの経営の比重が大きいので、 SYU・HA・RI では自分のパフォーマンスが最大限生かせるバランスで業務にあたっています。
オーナーがグリーンバイヤーの仕事を兼任することは、マネージャーやロースターを経験した次なるキャリアステップとしてはもちろん、組織を形成・成長させていくための「新しい在り方」の一つとしての可能性を秘めているのではないかと思っています。2つの仕事をすることで、組織のメンバーに還元できるものがより多くなるとも感じています。
「新しい在り方」を作っていくチャンスは誰にでも巡ってくるものではないので、最終的にSYU・HA・RIと歩みを共にすることを決めました。でもその決断ができたのも、ひとえに背中を押してくれる代表の辻本の柔軟さ、懐深さというところに帰着するのかなと思いますね。

グリーンバイヤーというと、様々な豆を独自のルートで買い付け、日本国内で流通させるために全国のロースターに販売するというイメージですが、SYU・HA・RIではいかがでしょうか?他のバイヤーや生豆業者と異なる手法で豆を仕入れ・流通させている点などあれば教えてください。
”手法”として大きく異なる点はそれほどないと思っています。
SYU・HA・RIとして求めるコーヒーの味わいや買い付けのコンセプトが明確にあるので、それにフィットする生豆を選んでいます。現在のマーケットでニーズがあるものでも、私たちが求める味わいとコンセプトにマッチしていないものは買い付けません。それは現地サプライヤーや国内のお客様との相互理解があるからこそ成り立っている点だなと思います。
生産者やサプライヤー、国内のお客様も含め、毎年お付き合いをさせていただいていく中で築かれるものを大切に、顔の見えるバイヤーとして対面しお話しさせていただくことにも重きを置いています。
自身のお店で扱う生豆を買い付けるロースターは見かけますが、生豆業社に所属してコーヒー買い付けを行う方をあまり見かけないのは、おそらく目的が異なるからではないかと推測します。買い付けをされる際に気を付けていることや、日本の消費者が好む味わいや特徴を意識するようなことがあるか、具体的なエピソードがあれば教えてください。
「1つのコンテナをどのように仕立てるのか」という視点は、常に買い付けのベースにあります。
それぞれのオリジンで買い付けるロット(ボリュームロットも買い付けるのか、マイクロロットのみ買い付けるのか、など)が異なるので、その中でのバランスと、もちろんクオリティと価格のバランスも意識しながら1つのコンテナを仕立てていきます。
買い付けのカッピングの際には、毎年お付き合いしているロースターさんの顔が思い浮かぶことがあります。これまで購入してくださった生産者のコーヒーや、店舗で出されているコーヒーをはじめ、実際にお話する中で各ロースターさんの好みの味わいのイメージがあるので、テイスティングをしながら国内のお客様の顔が浮かぶことがあるんです。
それぞれのロースターさんで求めるキャラクターが異なるので、SYU・HA・RIとしてのバリエーションを持たせた上で、それぞれの良いものを買い付けています。
生豆のソーシングから焙煎、抽出まで経験することで、それぞれの工程だけを経験していた頃と比べて、どのような気づきや学びがありましたか? そしてその気づきがどのようにお店づくりや買い付けに活かされているのでしょうか。
各工程に触れたことで、コーヒーが「奇跡のリレー」だということに改めて気づきました。正確には「気づいた」というよりも、それをより色濃く、確かなものとして「感じる」ようになったというべきでしょうか。コーヒーに対する感謝の念がより一層強くなったことが一番の学びですね。
生豆が一杯のコーヒー、それも美味しいと感じられる液体になるには、どの工程でエラーが起きても叶いません。それぞれの工程でどれほどの人々が、どれほどの手間や情熱をかけて次のセクションへと送り出し、それを受け取り、また送り出しているのか。そこには想像もつかないほどの道のりがあります。
各工程を体験し、そうした背景や事実への理解が少しずつ深まることで、お店で提供する目の前の1杯、ロースターさんへお届けする買い付け1ロット、全てのサプライチェーンでの“仕事の重みと難しさ”を改めて感じます。その重みと難しさは、お店づくりや買い付け全般において「コーヒーに従事する者の仕事に対する姿勢」として生かされていると思いますね。

この記事は、Standart Japan第30号のパートナーSYU・HA・RIの提供でお届けしました。